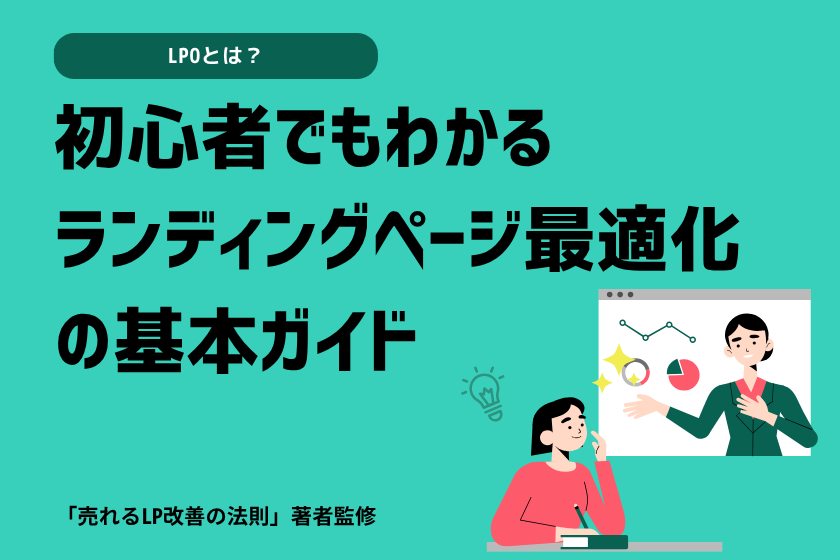広告を出しているのに、思ったほど申し込みが来ない――。
そんなときに見直すべきが「LPO(ランディングページ最適化)」です。
LPOとは、訪問者が最初に見るランディングページ(LP)を、より成果が出る形に改善していく取り組みのこと。
クリックはされているのにコンバージョンにつながらない原因の多くは、「LPでの離脱」です。
この記事では、
– LPOの意味や目的
– SEOとの違い
– どんな改善ができるのか
など、初心者の方にもわかりやすく解説します。
「広告効果を高めたい」「コンバージョンを増やしたい」という方は、まずここから理解を深めていきましょう。
目次
LPOとは?ランディングページ最適化の意味と目的
LPOは「Landing Page Optimization」の略で、日本語では「ランディングページ最適化」と訳されます。
Web広告や検索経由で流入してきたユーザーを、できるだけ高い確率で成果(コンバージョン)につなげるために、ランディングページの内容や構成を改善する取り組みです。
たとえば広告をクリックしてランディングページ(以下LP)に訪れても、
「なんだか怪しい…」「自分に関係なさそう」と感じれば、ユーザーはすぐにページを閉じてしまいます。
この“離脱”を防ぎ、ページに滞在してもらい、興味を持ち、アクションしてもらうために行うのがLPOです。
広義・狭義のLPとは?
LP(ランディングページ)には2つの意味があります。
-
広義のLP:検索結果や広告など、ユーザーが最初に訪れるすべてのページ
-
狭義のLP:広告用に作られた1枚構成の縦長ページ(例:セミナー申し込みページや商品販売ページ)
この記事で扱うLPOは、主に狭義の「縦長LP」に対する改善を想定しています。
LPOは広告運用とセットで語られることが多く、特にリスティング広告・SNS広告などで獲得効率を高めるには欠かせない施策です。
なぜLPOが重要なのか?【CVR向上・広告効率アップ】
Web広告やSNSからの流入があるのに、なかなか申し込みや購入につながらない…。
そんなとき、多くの場合は「ランディングページでの離脱」が原因です。
せっかく広告費をかけてユーザーを連れてきても、ページの内容や構成が悪ければ、興味を持たれる前に離脱されてしまいます。
LPOは、その“最初の1枚”を改善することで、コンバージョン率(CVR)を引き上げる極めて効率の良い施策です。
LPOによって得られる主なメリット
-
コンバージョン率(CVR)の向上
→ ページからの申込み・購入率が上がることで、同じ広告費でも成果が増える -
広告の費用対効果(ROAS)の改善
→ 1件あたりの獲得単価(CPA)が下がり、広告投資の効率がよくなる -
ユーザー満足度の向上
→ ストレスの少ない導線や内容によって、再訪や口コミにもつながりやすくなる
LPOは、広告だけでなくWeb集客全体のROIを押し上げるカギ。
今や「広告を出すならLPOは必須」といっても過言ではありません。
LPOとSEO・CRO・EFOの違い【図解あり】
LPO(ランディングページ最適化)は、CVR改善の施策のひとつですが、
似たような言葉に「SEO」「CRO」「EFO」などがあり、混乱しやすいポイントです。
ここでは、それぞれの違いと役割をわかりやすく整理しておきましょう。
| 施策 | 対象 | 主な目的 | 主な改善内容 |
|---|---|---|---|
| SEO(検索エンジン最適化) | サイト全体 | 自然検索流入を増やす | コンテンツ、キーワード、内部構造 |
| CRO(コンバージョン率最適化) | サイト全体 | サイトの成約率を上げる | ページ構成、導線、動線設計 |
| EFO(入力フォーム最適化) | フォーム部分 | フォーム離脱を減らす | 入力項目の簡略化、補助表示など |
| LPO(ランディングページ最適化) | LP(初着地点) | 広告や検索流入をCVにつなげる | 訴求、レイアウト、ファーストビューなど |
補足ポイント
LPOは「来たユーザーを離脱させない・行動させる」役割を担い、広告成果を大きく左右します。それぞれの施策は目的と対象が違うだけで、組み合わせて活用するのが理想的です。
LPOを始める前にやるべき準備
LPOは「いきなり見た目を変える」のではなく、データに基づいて仮説を立て、検証しながら改善していくのが基本です。
思いつきでデザインや文章を変更しても、逆に成果が下がってしまうケースもあるため、事前準備が非常に重要です。
ステップ1:現状分析を行う
まずは、**「なぜ今のLPが成果につながっていないのか?」**を客観的に把握するところから始めましょう。
-
Googleアナリティクス(GA4):滞在時間、直帰率、CVRなどの定量データ
-
ヒートマップツール:スクロール率、クリック箇所、注視エリアなどの視覚的データ
-
録画セッションツール:ユーザーの動きや迷いを可視化
これらのツールを活用することで、**「どこでユーザーが離脱しているのか」「どの部分が見られていないのか」**が見えてきます。
ステップ2:ユーザー視点での仮説設計
データが揃ったら、「なぜその行動を取ったのか?」という仮説を立てていきます。
例えば:
-
ファーストビューの訴求が弱くて興味を持たれない?
-
広告文とLPの内容にズレがある?
-
フォームが長くて面倒に感じられている?
-
スマホで見づらい?
-
説得力が足りず、不安が解消されていない?
これらの仮説が、次の「改善案を立てる」土台になります。
ステップ3:テストを前提とした改善準備
LPOは「やって終わり」ではなく、ABテストなどで効果検証を繰り返すPDCAサイクルが基本です。
-
ABテスト or 多変量テストを行うツール(Google Optimizeなど)を用意
-
改善案は「1つの要素ずつ」検証可能な形に分解
-
テスト中のLPとオリジナルLPを同時運用できる仕組みを整える
まずはこの3ステップを押さえることで、失敗しないLPOの土台が整います。
成果につながるLPOの改善ポイント5選
LPOでは、ちょっとした変更が大きな成果につながることがあります。
ここでは、特に効果が出やすい代表的な改善ポイントを5つ紹介します。
① ファーストビューを最適化する
ユーザーが最初に目にする「ファーストビュー」は、LPの成否を大きく左右します。
ファーストビューで重要なのが「ターゲットの特定」と「ベネフィットの訴求」です。
ターゲットの特定
ターゲットの特定とは、「このLPはあなたのためのページです」と伝える、ということです。例えば、「肌のハリが気になり出したあなたへ」「今の職場に未来がないと感じているあなたへ」「お子さんの成績が気になっているママへ」など。
ターゲットが「自分のことだ」と感じれば、そのLPに自分の役に立つことが書いてあると感じて読み進めてくれます。
ベネフィットの訴求
ベネフィットとは、顧客が手に入れるプラスの結果です。顧客は商品を通じて、何かができるようになったり、何かをしなくて良くなったり、理想の状態になることを望んでいます。
なので、「あなたはこうなれる」をキャッチーに伝えるコピーと理想的な状況をイメージできるビジュアルをファーストビューに置くようにしてください。
② オファーエリアを最適化する
オファーエリアとは、顧客が購入する商品やその取引条件を示し、申し込み導線へと促す部分です。商品名、商品画像、容量、サイズ、価格や数量などの情報と、申し込み行動を促すボタンを設置します。
この行動喚起する部分をCTA(コール・トゥ・アクション)と言い、オファーエリアの中でも目立つデザインにして、目を止めやすくするのがポイントです。
POINT
-
ボタン文言は「無料で試す」「今すぐ資料請求」など具体的に
-
色・サイズ・配置場所を工夫(視線の流れに沿わせる)
-
ボタンの前後にベネフィットや保証などの補足説明を入れる
③ 入力フォームのハードルを下げる(EFO)
フォームが長かったり、入力が面倒だと、それだけでユーザーは離脱します。申し込みに不要なアンケートなどは絶対に取らないでください。
POINT
-
入力項目を最小限に(名前・メールアドレスだけ等)
-
プレースホルダやエラーメッセージの最適化
-
「あと○分で完了」といった完了までの目安表示も効果的
④ 無駄なリンクや情報を減らす
LPは「迷わせない」のが鉄則。買うか?出るか?の二択を迫るページにしてください。メニューや他ページへのリンクが多すぎると、見込み客の注意が散ってしまうからです。
複数の商品を売ろうとするのもNGです。1つの商品のプランがいくつかあるのはOKです。LPは受け身ではなく攻めのページなので、1つの商品をその商品の見込み客に対して、興味づけし、説得し、購入してもらう1本の道筋になるようにしてください。
⑤ ABテストで仮説を検証する
LPOは“やって終わり”ではなく、“改善し続けること”が重要です。1つ1つのパーツを少しずつ改善することで、最終的なCVRの向上を目指す施策です。
ABテストとは
ABテストとは、2つのパターンを同時に運用し、どちらの方がより効率的にコンバージョンを集められるかを検証する方法です。同時に運用する理由は、可能な限りLP以外の環境を揃えることで、LPの違いによる結果の違いを明らかにするためです。
ABテストのやり方として、LPを2つ用意してそれぞれを媒体に入稿する方法があります。これが最もオーソドックスで誰でもすぐにできる方法です。
ですが、LPOを積極的に行っていくのであれば、ABテストツールの導入はマストです。ABテストツールとは、URLを変えずにLPの見た目だけを差し替えることができるツールです。
LPを複製する必要も、媒体にそれぞれ入稿する必要もないので、テストをスムーズに行うことができます。
必ず守っていただきたいLPOのルールが「1要素ずつテストする」ということです。いろんなパーツを変更したら、どのパーツの違いによって結果が変わったのかが分からなくなるからです。
1つのLPの中で、ファーストビューもオファーもCTAも変えてしまっていたら、Bパターンの結果が良かった時に、ファーストビューが良かったのか、オファーが良かったのか、CTAが良かったのかが分からなくなります。
なので、必ず何をテストするのかを決めて、1要素だけ変えたパターンでABテストをするようにしてください。
LPOでよくある失敗と注意点
LPOは効果が出やすい施策ですが、やり方を間違えると成果が出ないばかりか、逆効果になることも。ここでは、よくある失敗パターンと注意点を解説します。
❌ ① いきなり全部を変えてしまう
ABテストの原則は「1つの要素だけを変更する」こと。一度に見た目もコピーもCTAも変えてしまうと、何が成果に影響したのかがわからず、検証ができなくなります。
❌ ② データや仮説なしに“なんとなく”で改善する
「なんとなくこの見た目の方がいい気がする」という勘に頼った変更は、失敗のもとです。
必ずアクセス解析やヒートマップなどのデータをもとに、「なぜその改善をするのか?」を言語化してから着手しましょう。
❌ ③ ユーザー視点を忘れている
制作者側の「伝えたいこと」ばかりを並べても、ユーザーには響きません。LPOでは、“見込み客が何に困っていて、何を知りたいのか”という視点で情報設計をすることが重要です。
❌ ④ 流入元との整合性が取れていない
広告や検索結果から来たユーザーが、「思っていた内容と違う」と感じるとすぐに離脱します。たとえば広告で「無料体験」と訴求していたのに、LPで「まずは有料登録」と書かれていれば、違和感を感じて離脱します。
失敗しないために意識したいこと
-
1要素ずつ改善して効果を検証する
-
必ずデータと仮説に基づいて改善案を出す
-
流入元(広告・検索)との整合性を確認する
-
テスト結果は記録・共有し、PDCAを回す体制をつくる
「やったつもり」ではなく、「成果につながった」と言えるLPOを目指すことが大切です。
まとめ|LPOの基本を押さえて、広告効果を最大化
LPO(ランディングページ最適化)は、広告やWeb施策の成果を大きく左右する重要なプロセスです。どれだけ質の高い広告を出していても、LPが最適化されていなければ、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。
この記事では、LPOの基本から改善ポイントまでを初心者向けに解説してきました。
あらためて、押さえておくべきポイントを振り返っておきましょう:
-
LPOは、LPの内容や構成を改善してCVRを高める施策
-
SEOやCROとは役割が異なり、広告成果に直結する
-
改善前には必ずデータを確認し、仮説を立ててテストを行う
-
ファーストビュー、オファーエリア、フォームなどは特に重要な改善領域
-
1つずつ検証し、継続的にPDCAを回すことが成果につながる
LPOは“やったら終わり”ではなく、“やり続けることで結果が出る”取り組みです。
まずは今のLPを客観的に見直すところから始めて、ユーザー目線で1つずつ改善していきましょう。https://temahima.co.jp/lpo/lpo-future/