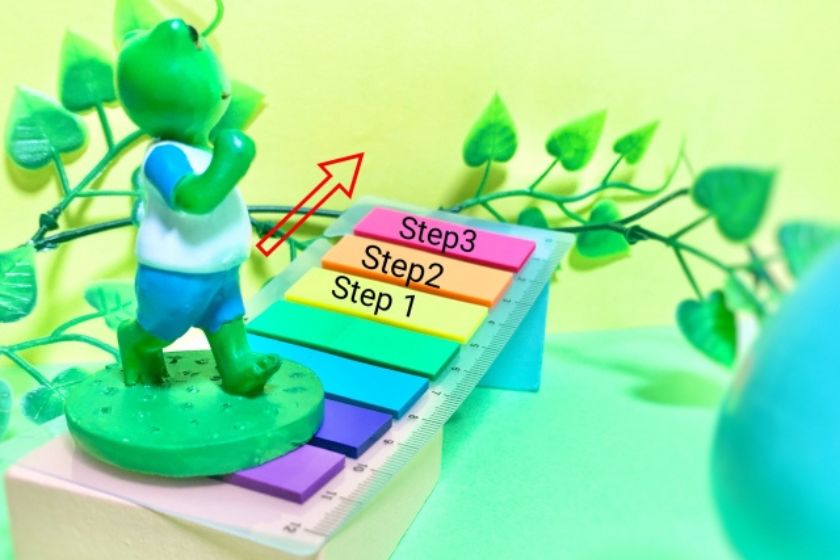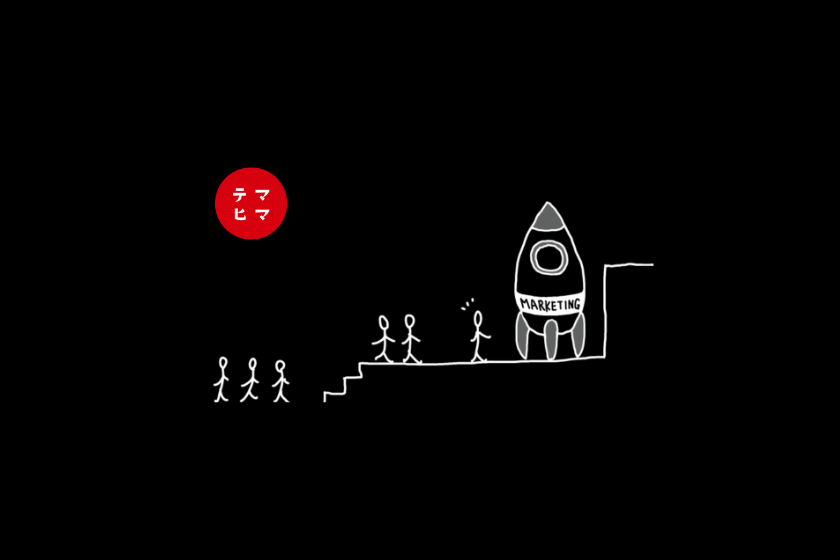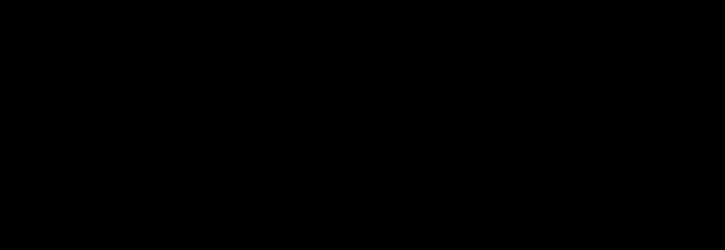マーケティングの仕事をしていると「導線」という言葉をよく口にしていると思います。
「導線」は、見込み客を顧客化するための道筋のような意味で使われています。
人によっては「動線」と表現している方もいるかもしれません。ですが、マーケティングの文脈においては、「導線」の方がより適した表現になります。
なぜ「導線」の方が適した表現なのかについてお話します。
導線と動線の意味
「どうせん」という言葉には「導線」と「動線」の漢字があります。
導線は”電流を流す際の導体として使われる金属線”が本来の意味です。
動線は”人や物が移動する際に辿る軌跡や経路”という意味です。都市計画や建築などで使われることが多い用語です。
言葉の意味からすると、”人がとる購入という行動への経路”という意味では「動線」の方がマーケティングの文脈においても合っているように感じます。
本来的には動線の方が言葉の使い方としては正しいのだと思います。
マーケティングで導線を使う理由
でも、マーケティングは見込み客が顧客化されるまでのプロセスを構築することで、意識の変化と行動の変化を促す活動です。売り手の促しによって、買いたい!と感じてもらい、買える状況を作る活動です。
なので、見込み客を導くという意味が強いため、あえて「導線」の方を使うようにしています。導いた結果、人が動くので「動線」の方がやはり言葉の意味的にも正しいのですが、動いている相手を呼び込むのではなく、動きたくなるように仕向けるという意思をより込めた言葉にするためには、「導線」の方がより適切だと考えています。
意味が通じるならどっちでもいいやん、と感じる方もいるかもしれません。
でも、漢字が変わればそこに込められた意味が変わってきます。その言葉の使い手の意思を言葉に乗せることもできます。同じような意味の単語が複数ある時、なぜその言葉を選んだのかも相手と共有することで、よりコミュニケーションの濃度が高まります。
何気なく使っている言葉の意味を改めて調べてみると、意図していたニュアンスと違っていることもよくあります。
日本語は特にそうだと思いますが、同じ意味で使われている複数の言葉があります。全く同じ意味であれば1つで良いはずです。でも、複数の言葉が存在し続けているということは、使うシーンや心情によって使い方が変わるからです。
見込み客が言葉に対して認識している意味もまた違うものとなります。相手がその言葉にどんなイメージを持っているのか、どんな時に使っているのか、そもそもそういう言葉に耳馴染みがあるのかなどを考えて、届けているメッセージを見直してみると新しい発見があると思います。