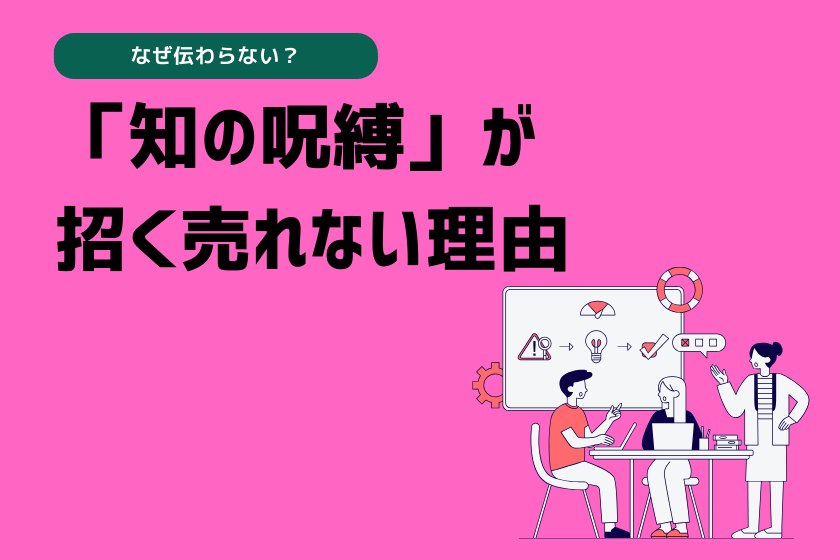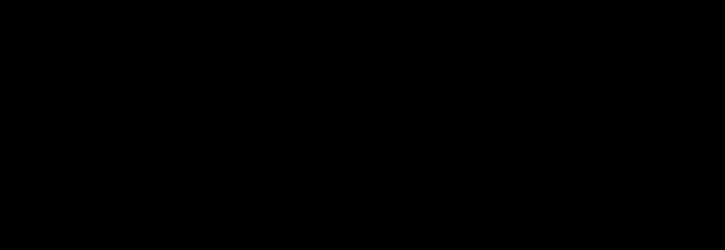目次
知の呪縛とは?
「知の呪縛」という言葉をご存知でしょうか?
これは、一度知ってしまうと知る前の状態に戻れない現象のことです。
例えば、手を叩いてリズムを刻み、相手にその曲名を当ててもらうゲームを想像してください。
叩いている本人は頭の中で音楽が流れているため「これで伝わるはず」と思い込みます。
しかし聞き手には「タンッタタンッ」という単調なリズムしか聞こえず、正解にたどり着くのは困難です。
このとき叩き手は「なんでわからないんだ?」と不思議に思います。
まさに「知の呪縛」にかかってしまい、相手の立場を忘れてしまっている状態です。
コミュニケーションが噛み合わないのはなぜか?
私たちの日常のコミュニケーションでも、この「知の呪縛」は頻繁に起こります。
-
上司が部下に専門用語で指示しても、意図が伝わらない
-
営業担当が機能の話ばかりしても、顧客が「それで自分に何のメリットがあるのか」が理解できない
-
同じ会議に出ているのに、人によって受け取り方が全く違う
こうしたズレは、前提となる知識の差が原因です。
情報を共有しているつもりでも、相手の頭の中にある背景が違えば、言葉の意味はすれ違ってしまいます。
だからこそ、議論や説明が噛み合わないときは「相手が持っている知識の前提」を確認し、共通認識をつくる必要があります。
正直、手間のかかる作業ですが、これを省くと確実にコミュニケーションの質は落ちてしまいます。
マーケティングにおける「知の呪縛」
この現象は、マーケティングや営業の現場でも大きな影響を与えています。
売り手(企業やマーケター)は、自社商品について深く理解しています。
「なぜ優れているのか」「どんな効果があるのか」まで熟知しています。
しかし、買い手(顧客)は違います。
多くの顧客は、自分が抱えている課題さえ明確に理解していないこともあります。
-
「何が問題なのか」
-
「どんな選択肢があるのか」
-
「それぞれの違いは何か」
こうした前提が抜け落ちた状態で、いきなり商品のメリットを説明しても伝わるはずがありません。
売り手は「これだけ良い商品なのに、なぜ伝わらないんだ?」と不思議に思いますが、それはまさに知の呪縛の罠に陥っているのです。
顧客に価値を伝えるためのアプローチ
では、この知識の差をどう埋めればよいのでしょうか?
ポイントは「売る前に教育する」ことです。
1. 専門用語をかみ砕く
顧客にとっては初めて聞く言葉も多いもの。
可能な限り平易な表現に変え、イメージしやすい事例を添えることが大切です。
2. 前提を共有する
「なぜこの商品が必要なのか?」を、顧客の現在地に合わせて説明します。
例:ダイエット食品を売るなら「なぜ運動だけでは効果が出にくいのか」という背景から伝える。
3. 第三者の声を借りる
売り手の言葉は疑われやすいため、レビューや事例を通じて「他の人もそう感じている」という社会的証明を提供します。
4. 比較対象を用意する
競合や他の解決策との違いを明確にしないと、顧客は選択できません。
「なぜこの商品を選ぶべきか」がわかる比較情報を提示しましょう。
まとめ:まず「知識の差」を知ることから
売れない理由の多くは「商品の魅力が足りない」わけではなく、顧客にその価値が届いていないからです。
その背景には「知の呪縛」があります。
👉 顧客に提案をするとき、次の問いを自分に投げかけてみてください。
-
顧客が持っている前提知識はどこまでか?
-
自分の説明は、その知識レベルに合っているか?
-
専門用語や前提を飛ばしていないか?
売り手の頭の中にある「常識」を疑うことから、顧客に本当に伝わるマーケティングが始まります。